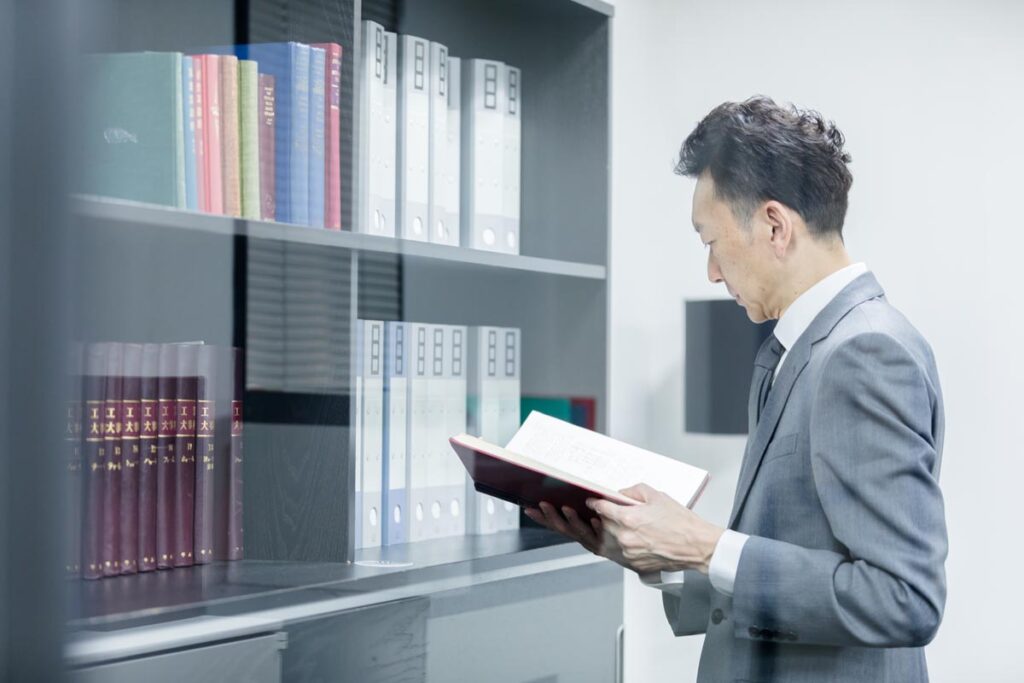新着情報

2024.05.24
ー社労士として働くには登録必要!費用やメリットを解説ー
社労士の試験に合格したあとは登録が必須です。
登録するとどのようなメリットがあるのか、必要な費用はあるのか詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。
社労士として登録するためには3つの費用が必要です。
・事務指定講習費用
・連合会加入の登録手数料と登録免許税
・社労士会加入の入会金と年会費
さらに、登録しておくと研修を通してスキルアップできたり、人脈づくりができたりと多くのメリットがあります。
本記事では社労士の登録費用とメリットを詳しく解説します。
登録条件や種類も紹介しているため、参考にしてください。
社労士として働くためには登録が必須!必要になる費用を解説
社労士は試験に合格しただけでは働けません。
社労士登録して初めて「社会保険労務士」と名乗れ、業務を行えます。
ここでは登録にかかる費用を詳しく解説するため、参考にしてください。
事務指定講習費用(77,000円)
社労士として活動するためには、事務指定講習の受講が必要で費用は77,000円です。
登録要件にある「2年間の実務経験」が満たせない場合に事務指定講習を受講する必要があります。
専門知識を実践に活かすためにも、実務経験の講習は必須です。
労働基準法や社会保険法の適用方法を学びながら、実務に必要なスキルと知識を身につけていきます。
連合会加入の登録手数料と登録免許税(各30,000円)
社労士登録には連合会へ加入し、正式に社労士と認定される必要があります。
登録手数料と登録免許税はそれぞれ30,000円です。
登録後は社労士の活動が公式に認められ、名刺にも肩書きとして堂々と記載できます。
社労士としての業務を合法的に行うためにも、必ずか加入しましょう。
社労士会加入の入会金と年会費(都道府県により異なる)
各都道府県の社労士会に加入するために必要で、費用は地域によって異なります。
たとえば、愛知県は社会保険労務士法人の社員の場合、入会金は10万円です。
情報共有や研修に参加できるため、スキルアップが目指せます。
継続的に学べるのはもちろん情報交換の場としても活用でき、社労士の質を向上できます。
社労士として登録する4つのメリット
社労士として登録すると得られるメリットは4つあります。
1.社労士として名乗れる
社労士登録すると正式に「社会保険労務士」と名乗れます。
社労士登録していない状態では名刺にも社会保険労務士と記載できず、あくまで社労士試験の合格者にとどまります。
登録すると社労士として活動できるため、労働法や社会保険に関する専門知識がある証となります。
企業の人事部門や労務管理、クライアントなどからも高い信頼を得られるでしょう。
2.独占業務を担当できる
社労士登録すると独占業務を担当できます。
独占業務は社労士には資格所有者のみが業務できる仕事です。
・1号業務|提出手続きの代行
・2号業務|帳簿書類の作成
雇用保険や労災保険の新規加入、解除手続きのほか源泉徴収票の発行など独占業務を行えるのは社労士登録した方のみです。
専門知識を活かした多くのサービスを提供できます。
3.研修を通してスキルアップできる
社労士会登録すると、定期的な研修やセミナーを受けられます。
法律改正や実務知識を常に学び続けられ、クライアントに最新の情報を提供できます。
労働法や社会保険分野は法改正が多く、常に情報収集し知識を身につける必要があります。
研修を通して継続的なスキルアップができると、専門家としての価値を高められる点がメリットです。
4.社労士同士のつながりが増える
社労士登録すると定例会議や研修などで、さまざまな人と交流を深められます。
同業者との交流を通じて情報交換やアドバイスを受けると、業務の幅が広がります。
最新の知識やビジネスチャンスを得られるほか、開業している人の活躍に刺激を受けることもあるでしょう。
人脈が広がると社労士として働き方の視野が広がるところが魅力の一つです。
社労士登録に必要な条件
社労士の登録は誰でもできるわけではなく、必要条件があるため詳しく解説します。
2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験があるか
社労士として登録するには、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要です。
たとえば企業の人事部門や労務管理部門で雇用保険、健康保険などに関する事務経験があるかどうかが問われます。
実務経験になるかどうか判断できない場合は、都道府県社会保険労務士会または全国社会保険労務士連合会に確認しましょう。
事務指定講習を履修しているか
上記の実務経験がない場合は事務指定講習が必要です。
社労士試験で学ぶ知識と、実際の実務で必要な知識は同じではありません。
事務指定講習では実際の実務で必要となる新規適用手続き、入社や退職が発生した際の手続きなどを学べます。
実務経験がなくても事務指定講習を受けると、社労士業務の基本スキルを身につけられます。
実務経験がない、または少ない方でも受講により条件を満たせると登録が可能です。
社労士登録の種類3つ
社労士登録には3つの種類があります。
それぞれ詳しく解説するため、参考にしてください。
1.開業登録|独立する場合
開業登録は、独立して社労士業務を行うための登録です。
自ら事務所を構え、クライアントに対して直接サービスを提供できます。
独立開業する場合はさまざまな事業所からの依頼に対して業務を行え、自由度の高さがメリットがメリットです。
信頼関係を築いていくことで多くの顧客を獲得でき、高収入が見込めるでしょう。
2.勤務登録|所属会社内の業務のみ行う場合
勤務登録は、社労士事務所や民間会社の勤務社労士としての登録です。
所属する会社内での労務管理や社会保険手続きなどの業務を担当します。
安定した収入や組織内でのキャリアアップが見込める一方、独立開業する場合より自由度は低くなるでしょう。
3.その他登録|情報取得や人脈づくりをしたい場合
その他登録は、社労士業務を行わない場合の登録です。
情報取得や人脈づくりを目的としている方は、その他登録を行います。
社労士会や関連団体のイベント、研修に参加できるため業界の知識を得られるほか、同業者との人脈づくりができます。
今すぐではなくても、将来的に社労士として働きたい方はその他登録がおすすめです。
まとめ
社労士登録は「社会保険労務士」として働くうえで必須です。
試験に合格しただけだと独占業務はできず、社労士とも名乗れません。
登録には下記3つが必要となるため、覚えておきましょう。
・事務指定講習費用
・連合会加入の登録手数料と登録免許税
・社労士会加入の入会金と年会費
社労士登録は同業者との交流を深められ、人脈づくりにもつながります。
情報収集にも効果的のため、忘れずに登録しましょう。